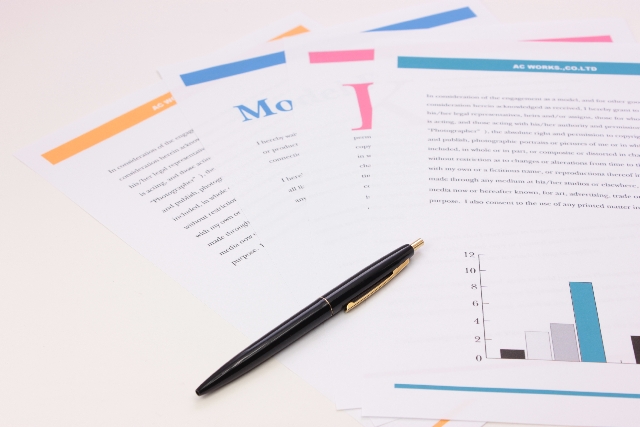


入社して三週間ほどで会社を辞めました。
その後一ヶ月ほど経ちますが、離職票が届きません。
これは異常ですか?
もうその会社とは関わりたくないため電話したくないのですが、ハローワークで離職票は貰えるで
しょうか?
どういう風に言えばもらえますか?
その後一ヶ月ほど経ちますが、離職票が届きません。
これは異常ですか?
もうその会社とは関わりたくないため電話したくないのですが、ハローワークで離職票は貰えるで
しょうか?
どういう風に言えばもらえますか?
離職票の発行の前に、雇用保険の被保険者でしたか?
雇用保険の被保険者が退職しないと離職票は発行されません。。
被保険者でないものが退職しても作ることもできないということです。。
まずはそちらの確認を、、、ハローワークで被保険者であったかどうかの確認はできます。
雇用保険の資格取得手続きは、雇用した日の属する月の翌月10日までに手続きすればよいことになっています。
2月1日に雇用されれば、手続きは3月10日まで、、
この手続きの前に退職してしまえば、雇用保険の資格取得手続きも行っていないのではないでしょうか?
雇用保険の被保険者が退職しないと離職票は発行されません。。
被保険者でないものが退職しても作ることもできないということです。。
まずはそちらの確認を、、、ハローワークで被保険者であったかどうかの確認はできます。
雇用保険の資格取得手続きは、雇用した日の属する月の翌月10日までに手続きすればよいことになっています。
2月1日に雇用されれば、手続きは3月10日まで、、
この手続きの前に退職してしまえば、雇用保険の資格取得手続きも行っていないのではないでしょうか?
志望動機の書き方について質問なのですが、ハローワークの求人に応募し、いざ、志望動機を書こうと会社名からネットで調べたらその会社の地図しか検索できず、ホームページはおろか、何の情報もありませんでした。
求人票を見ても、あっさり抽象的な事しか書いてないのですが、どう志望動機を書けばいいでしょうか?何か他に情報を得る手段はあるでしょうか?
求人票を見ても、あっさり抽象的な事しか書いてないのですが、どう志望動機を書けばいいでしょうか?何か他に情報を得る手段はあるでしょうか?
同様の質問はたくさんあります。
そういう人に逆に質問したいのですが、
なぜその会社に応募しようと思ったのですか?
応募しようと思った理由も志望動機の一部ですよね。
何枚か求人票がある中から目をつぶって1枚取ったとかなら別ですが。
てか志望動機とか堅苦しい話の前に、応募する「理由」がありますよね。
何も考えずに応募するわけはないですから、
その「理由」をちょっと堅苦しく書けばいいのです。それが志望動機になります。
ネットなんかに頼る必要もありません。
求人票を見て応募しようと思った「理由・きっかけ」で十分です。
例えば、ですが
「家が近いから」なら「地域をよく知っているので、その盛り上げのために頑張りたい」
「前やってた仕事だから」=「以前の経験が生かせる仕事についてさらにスキルを磨きたい」
「給料がいいから」=「御社には事業内容や待遇面も含めて、魅力を感じている」
「その業界が好き」=「御社とその業界は私が経験してみたい仕事があり、今回チャンスだと思った」
など。
まだ、面接に行ったらツッこまれるかもしれないので、回答は考えておきましょう。
そういう人に逆に質問したいのですが、
なぜその会社に応募しようと思ったのですか?
応募しようと思った理由も志望動機の一部ですよね。
何枚か求人票がある中から目をつぶって1枚取ったとかなら別ですが。
てか志望動機とか堅苦しい話の前に、応募する「理由」がありますよね。
何も考えずに応募するわけはないですから、
その「理由」をちょっと堅苦しく書けばいいのです。それが志望動機になります。
ネットなんかに頼る必要もありません。
求人票を見て応募しようと思った「理由・きっかけ」で十分です。
例えば、ですが
「家が近いから」なら「地域をよく知っているので、その盛り上げのために頑張りたい」
「前やってた仕事だから」=「以前の経験が生かせる仕事についてさらにスキルを磨きたい」
「給料がいいから」=「御社には事業内容や待遇面も含めて、魅力を感じている」
「その業界が好き」=「御社とその業界は私が経験してみたい仕事があり、今回チャンスだと思った」
など。
まだ、面接に行ったらツッこまれるかもしれないので、回答は考えておきましょう。
ハローワークで去年内定貰ったんですが蹴ってしまった会社が求人出してたんですが応募しても問題ないでしょうか?
去年内定やった奴だとばれますかね?
規模は小さい会社です
人事は去年と同じ人がやっています
去年内定やった奴だとばれますかね?
規模は小さい会社です
人事は去年と同じ人がやっています
応募自体は問題ないと思います。
ただし採用されるか、更に言えば面接まで辿り着けるかどうかは別問題です。
質問者様に内定を辞退された会社からすれば、正直印象は悪いはずですし、人事担当者でしたらまず覚えている事で間違いないと思います。
どうしても応募したいのであれば、昨年内定を辞退した明確な、かつ相手が納得出来る理由を用意しておく必要があります。
可能性は”0”ではありませんが、かなり厳しい道のりになると思います。
ご健闘をお祈り致します!!!
ただし採用されるか、更に言えば面接まで辿り着けるかどうかは別問題です。
質問者様に内定を辞退された会社からすれば、正直印象は悪いはずですし、人事担当者でしたらまず覚えている事で間違いないと思います。
どうしても応募したいのであれば、昨年内定を辞退した明確な、かつ相手が納得出来る理由を用意しておく必要があります。
可能性は”0”ではありませんが、かなり厳しい道のりになると思います。
ご健闘をお祈り致します!!!
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
各都道府県のハローワークで募集している「介護福祉士」の2年間の職業訓練を受講しようか考えています。
HPで調べてものの問い合わせや窓口へはまだ行けず詳しくわかりません。
経験者の方や詳しい方がいたら教えてください。
小さい子供のいる専業主婦なのですが、学校に通うのは毎日朝から夕方までなど決まっているのでしょうか?
受講時間の総合計などの記載がありましたが、そのあたりがわかりませんでした。
また年齢層はさまざまなのでしょうか?
小さい子供のいるかたはそれぞれで預けて受講しているのでしょうか?
また、この国家資格が無事に取れれば、働きに出られる可能性(需要)は大きく広がるくらい価値ある資格になりますでしょうか?
HPで調べてものの問い合わせや窓口へはまだ行けず詳しくわかりません。
経験者の方や詳しい方がいたら教えてください。
小さい子供のいる専業主婦なのですが、学校に通うのは毎日朝から夕方までなど決まっているのでしょうか?
受講時間の総合計などの記載がありましたが、そのあたりがわかりませんでした。
また年齢層はさまざまなのでしょうか?
小さい子供のいるかたはそれぞれで預けて受講しているのでしょうか?
また、この国家資格が無事に取れれば、働きに出られる可能性(需要)は大きく広がるくらい価値ある資格になりますでしょうか?
順番を変えてお答えします。
>この国家資格が無事に取れれば、働きに出られる可能性(需要)は大きく広がるくらい価値ある資格になりますでしょうか
→ そのとおりです。俗に言われる「ケアワーカー」の国家資格で、就職の際には非常に優遇される資格です。
>学校に通うのは毎日朝から夕方までなど決まっているのでしょうか
→ そのとおりです。職業訓練ですが、実態は専門学校や短期大学の授業とほぼ同一のカリキュラムです。
>年齢層はさまざまなのでしょうか?小さい子供のいるかたはそれぞれで預けて受講しているのでしょうか?
→ 年齢層やお子さんのいるかいないかは、さまざまです。
最後に、
介護福祉士については、短期大学や専門学校を卒業と同時に資格を取得できる資格「でした」ので、公共職業訓練校がそれらの短大や専門学校に委託するなどして行っている訓練です。
しかし、法改正により、23年度生からは短大・専門学校を卒業しても自動的に国家資格を取得することはできなくなり、あくまで国家試験に合格しないと資格が得られなくなっています。
つまり、昨年度に訓練を受講開始した方々は、修了しさえすれば国家資格が得られるのに対し、来年度もし同様の職業訓練があったとしても、それを受講する訓練生たちは修了後に国家試験に合格しないと資格は得られなくなっているわけです。
そうしますと、学校を卒業した方や実務経験のある方たちと試験において競い合って合格を勝ち取らなければならない、という高いハードルになってしまう職業訓練講座に、果たして応募者が集まるだろうか、高い合格率を結果として出してみせることができるだろうか、という大きな不安要素が実施機関側には生じます。
だからこそ、来年度の実施予定情報がどこにも明らかにされていないのではないのかと推測します。
ここからは私の個人的感想ですが、来年度は同じような職業訓練講座そのものがもはや存在しない、という可能性も十分に考えなければならないと思います。
>この国家資格が無事に取れれば、働きに出られる可能性(需要)は大きく広がるくらい価値ある資格になりますでしょうか
→ そのとおりです。俗に言われる「ケアワーカー」の国家資格で、就職の際には非常に優遇される資格です。
>学校に通うのは毎日朝から夕方までなど決まっているのでしょうか
→ そのとおりです。職業訓練ですが、実態は専門学校や短期大学の授業とほぼ同一のカリキュラムです。
>年齢層はさまざまなのでしょうか?小さい子供のいるかたはそれぞれで預けて受講しているのでしょうか?
→ 年齢層やお子さんのいるかいないかは、さまざまです。
最後に、
介護福祉士については、短期大学や専門学校を卒業と同時に資格を取得できる資格「でした」ので、公共職業訓練校がそれらの短大や専門学校に委託するなどして行っている訓練です。
しかし、法改正により、23年度生からは短大・専門学校を卒業しても自動的に国家資格を取得することはできなくなり、あくまで国家試験に合格しないと資格が得られなくなっています。
つまり、昨年度に訓練を受講開始した方々は、修了しさえすれば国家資格が得られるのに対し、来年度もし同様の職業訓練があったとしても、それを受講する訓練生たちは修了後に国家試験に合格しないと資格は得られなくなっているわけです。
そうしますと、学校を卒業した方や実務経験のある方たちと試験において競い合って合格を勝ち取らなければならない、という高いハードルになってしまう職業訓練講座に、果たして応募者が集まるだろうか、高い合格率を結果として出してみせることができるだろうか、という大きな不安要素が実施機関側には生じます。
だからこそ、来年度の実施予定情報がどこにも明らかにされていないのではないのかと推測します。
ここからは私の個人的感想ですが、来年度は同じような職業訓練講座そのものがもはや存在しない、という可能性も十分に考えなければならないと思います。
関連する情報