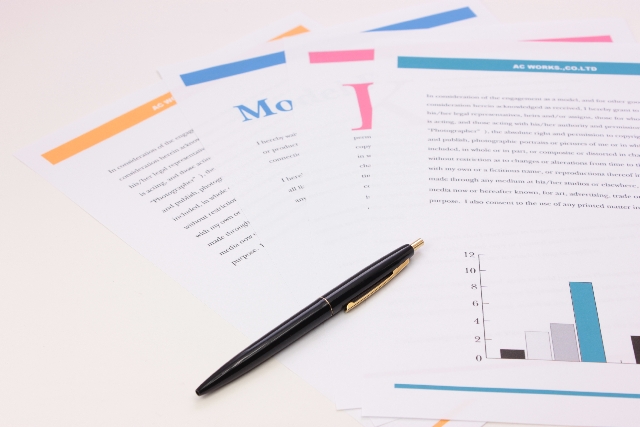


私は現在34才になります。てんかん病を持っていて作業所で就労に向けて訓練中ですが、このまま作業所で訓練し働けるように頑張るか、
このままダラダラ年をとっていき生活保護が受給されるのを待っているかどちらがいいと思いますか?
このままダラダラ年をとっていき生活保護が受給されるのを待っているかどちらがいいと思いますか?
私だったらこのまま作業所で就労に向けての訓練の道を
選びますよ。
体調と相談しながらということにはなると思いますが、
毎日作業所に通うということでメリハリのある生活が
できると思います。
生活保護を選ばれる場合でも、作業所という
毎日通うことのできる場所を持っていたほうが
いいですよ。
選びますよ。
体調と相談しながらということにはなると思いますが、
毎日作業所に通うということでメリハリのある生活が
できると思います。
生活保護を選ばれる場合でも、作業所という
毎日通うことのできる場所を持っていたほうが
いいですよ。
中途採用の面接について質問させてください!
私はハローワークを通して、某企業を受けてみました。
書類選考が通り、
一次面接では、とても良い印象だと言われ、履歴書を見た時点で採用した
いとも言われていました。
合否判定の結果は一週間後、連絡との事でしたが、
面接を受けてから、2日後に
二次面接をしたいとの事を言われました。
こちらの営業所は採用としていたのですが、
社長さんの方からも面接をして見て見たいと言われたそうです!
落ちる可能性は限りなく低いですよ!と営業所の面接を担当された方からも言われました
二次面接は予定をしていなかったはずなので、何故、二次面接を行う様にしたのか不安です(ーー;)
どんな二次面接になるのでしょうか?
長文申し訳ありません。
私はハローワークを通して、某企業を受けてみました。
書類選考が通り、
一次面接では、とても良い印象だと言われ、履歴書を見た時点で採用した
いとも言われていました。
合否判定の結果は一週間後、連絡との事でしたが、
面接を受けてから、2日後に
二次面接をしたいとの事を言われました。
こちらの営業所は採用としていたのですが、
社長さんの方からも面接をして見て見たいと言われたそうです!
落ちる可能性は限りなく低いですよ!と営業所の面接を担当された方からも言われました
二次面接は予定をしていなかったはずなので、何故、二次面接を行う様にしたのか不安です(ーー;)
どんな二次面接になるのでしょうか?
長文申し訳ありません。
今から悩んでも仕方ないので、全力を尽くすしかないのですが、
読んだ通りならば、「面接をしてみたい」・・・と言う事だと思います。
何も貴方に落ち度や貴方に対し不満・・・と言う事ではなく、社長の気まぐれや
「会社の長なのだから、顔合わせをしておきたい」・・・など軽い所からの
話だと思います。
面接担当者の言う通り、不採用になる可能性は低いかとは思いますが、
かといって、されど面接です。面接担当者が貴方の事をべた褒めだったと
しても社長が「気に入らない」・・・となれば、どんでん返しも多いにあり得ます。
あまり貴方に心配をさせたくはないのですが、自分が学生の頃、
某建機メーカーの海外事業部の面接を受けました。元々、海外事業部員は
募集していなかったのですが、たまたま自分が説明会で語学をPRしたことから、
特別に自分だけの為に応募職種を増やして面接をしてもらえる事になりました。
1次面接は人事と日本語で・・・2次面接は海外事業部員と人事と英会話面接を・・・
3次面接は海外の支店から日本に来ていた外人の従業員と海外の支店の
支店長と英会話面接を行いました。
全て順調にパスし、進んでいたのに、4次面接の最終面接で
社長に何故か嫌われ、いきなり不採用となりました。ほんと未だに納得が
いかないのですが、そういう事もあります。
逆に別の会社では面接の前に取締役と会食をする機会があり、
そこで、「うん。気に入ったから採用するよ。ただ、一応、他の部員にも
顔合わせをてもらわなければならないから、形だけの面接をするから」
・・・と面接をし、その場で内定を貰った事もあります。
なので、社長面接で社長にある程度気に入られれば、後は
「現場が良いって言っているのだから良いだろう」・・・と言う事で内定だと
思います。
まぁ、あまり堅苦しくならず、元気よく、笑顔で礼儀正しくされてください。
多少きつい事を言われても顔を曇らせず、「そうなんですか。勉強になります。
まだまだ未熟者ですから、どんどんご指導お願いします」・・・くらいの意気込みで
挑まれてください。
あと一歩ですから、がんばって。
読んだ通りならば、「面接をしてみたい」・・・と言う事だと思います。
何も貴方に落ち度や貴方に対し不満・・・と言う事ではなく、社長の気まぐれや
「会社の長なのだから、顔合わせをしておきたい」・・・など軽い所からの
話だと思います。
面接担当者の言う通り、不採用になる可能性は低いかとは思いますが、
かといって、されど面接です。面接担当者が貴方の事をべた褒めだったと
しても社長が「気に入らない」・・・となれば、どんでん返しも多いにあり得ます。
あまり貴方に心配をさせたくはないのですが、自分が学生の頃、
某建機メーカーの海外事業部の面接を受けました。元々、海外事業部員は
募集していなかったのですが、たまたま自分が説明会で語学をPRしたことから、
特別に自分だけの為に応募職種を増やして面接をしてもらえる事になりました。
1次面接は人事と日本語で・・・2次面接は海外事業部員と人事と英会話面接を・・・
3次面接は海外の支店から日本に来ていた外人の従業員と海外の支店の
支店長と英会話面接を行いました。
全て順調にパスし、進んでいたのに、4次面接の最終面接で
社長に何故か嫌われ、いきなり不採用となりました。ほんと未だに納得が
いかないのですが、そういう事もあります。
逆に別の会社では面接の前に取締役と会食をする機会があり、
そこで、「うん。気に入ったから採用するよ。ただ、一応、他の部員にも
顔合わせをてもらわなければならないから、形だけの面接をするから」
・・・と面接をし、その場で内定を貰った事もあります。
なので、社長面接で社長にある程度気に入られれば、後は
「現場が良いって言っているのだから良いだろう」・・・と言う事で内定だと
思います。
まぁ、あまり堅苦しくならず、元気よく、笑顔で礼儀正しくされてください。
多少きつい事を言われても顔を曇らせず、「そうなんですか。勉強になります。
まだまだ未熟者ですから、どんどんご指導お願いします」・・・くらいの意気込みで
挑まれてください。
あと一歩ですから、がんばって。
退職届けの受理についての質問です。
先日(6月15日)に直属の上司に辞意表明し、(6月末退職と記載の)退職届提出した所「自分では受理できないので更に上の上司に報告する」と言われて3日、直属の上司及び更に上の上司何も動きがありません。社内規定では14日前までに退職届け提出と記載ありますが、この場合自身で製作した届けの退職記載日(6月末)以降出社拒否は可能でしょうか?又、未受理を理由に拒否された場合の良い反論はありますでしょうか?できれば会社に反論できる様法律関係の説明も交えて教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
先日(6月15日)に直属の上司に辞意表明し、(6月末退職と記載の)退職届提出した所「自分では受理できないので更に上の上司に報告する」と言われて3日、直属の上司及び更に上の上司何も動きがありません。社内規定では14日前までに退職届け提出と記載ありますが、この場合自身で製作した届けの退職記載日(6月末)以降出社拒否は可能でしょうか?又、未受理を理由に拒否された場合の良い反論はありますでしょうか?できれば会社に反論できる様法律関係の説明も交えて教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
期間を定めない雇用契約なら、日給月給なら民法627条1項、完全月給制なら同2項が適用されます。日給月給なら、人事権を持つ者に意思が到達してから2週間後に任意退職となります(提出した日からの2週間ではありません)。
民法の規定は強行規定であるという地裁判例はあります。任意規定という考え方もありますが、就業規則が14日前までに提出となっているので、直属の上司に提出してから14日後に退職ということになります。
退職願ではなく、退職届となっているので、労働契約の合意解約の申し込みではなく、辞職意思の通知ということになりますから、承諾(受理)の余地はなく、通知した時点で有効であると主張することは可能ではないかと思います。
法的には、任意退職は人事権を持つ者に通知した日は数えずに2週間後が任意退職ですので、直属の上司がその日のうちに人事権を持つ者(経営者か人事部)に退職届をまわしていないのであれば、任意退職の効力の生じる日は提出日からの2週間後よりあとの日になるということにはなりますが、就業規則が14日前までに提出となっていますので、退職届に記載した退職日(6月30日)の次の日(7月1日)から出社しなくてもさしつかえないということになろうかと思います。
会社が退職処理を拒むということはあるかもしれませんが、その場合は、雇用保険手続きはハローワークから、社会保険は年金事務所から、源泉徴収票は税務署から催促してもらうしかないと思います。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
民法の規定は強行規定であるという地裁判例はあります。任意規定という考え方もありますが、就業規則が14日前までに提出となっているので、直属の上司に提出してから14日後に退職ということになります。
退職願ではなく、退職届となっているので、労働契約の合意解約の申し込みではなく、辞職意思の通知ということになりますから、承諾(受理)の余地はなく、通知した時点で有効であると主張することは可能ではないかと思います。
法的には、任意退職は人事権を持つ者に通知した日は数えずに2週間後が任意退職ですので、直属の上司がその日のうちに人事権を持つ者(経営者か人事部)に退職届をまわしていないのであれば、任意退職の効力の生じる日は提出日からの2週間後よりあとの日になるということにはなりますが、就業規則が14日前までに提出となっていますので、退職届に記載した退職日(6月30日)の次の日(7月1日)から出社しなくてもさしつかえないということになろうかと思います。
会社が退職処理を拒むということはあるかもしれませんが、その場合は、雇用保険手続きはハローワークから、社会保険は年金事務所から、源泉徴収票は税務署から催促してもらうしかないと思います。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
関連する情報