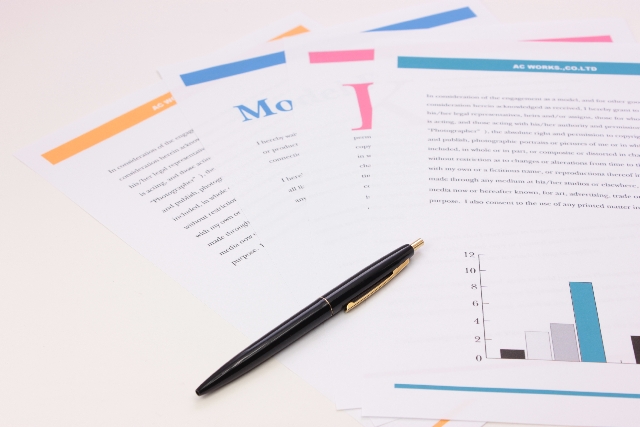


退職後扶養手続き、失業給付について…
この度、長年勤めた会社を退職することになりました。(退職日5月31日)
会社からは被保険者資格喪失証明書を頂き、後日離職票が届くそうです。
扶養に入ろうと思い、主人の会社から、『健康保険被扶養者(異動)届』を頂きました。
その際『退職証明書』と『雇用保険受給資格者証』の提出をして下さいとのこと…
今後失業給付金を受け取りたいなぁと思っているのですが(受給中はもちろん扶養を抜けます!)、初めてのことで、何を先にやったらいいのか全く分からず困っております。
お力をお貸し頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
この度、長年勤めた会社を退職することになりました。(退職日5月31日)
会社からは被保険者資格喪失証明書を頂き、後日離職票が届くそうです。
扶養に入ろうと思い、主人の会社から、『健康保険被扶養者(異動)届』を頂きました。
その際『退職証明書』と『雇用保険受給資格者証』の提出をして下さいとのこと…
今後失業給付金を受け取りたいなぁと思っているのですが(受給中はもちろん扶養を抜けます!)、初めてのことで、何を先にやったらいいのか全く分からず困っております。
お力をお貸し頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
退職は自己都合でしょうか?
自己都合であれば申請から受給まで4カ月ほどかかります。
その間は扶養に入っていられます。
すぐに受給するのであればハローワークに行き(離職票などもって)手続きをすればその後説明会があり、受給資格者証が貰えます。
原本を提出すると受給するときに面倒なので、コピーではだめなのか、原本なら確認後すぐ返却してもらえるのか確認してください。
そして、受給するときは扶養を外れるように旦那さんの会社に報告し、外れます。もし受給後も扶養に入るようならまた受給資格者証を提出します(受給完了したというのが記載されますので、それが証明になります。)
整理すると...
旦那さんの会社に確認→離職票が届く→職安にいき手続き→一週間後くらいに説明会があり、そこで受給資格者証を貰える→原本なりコピーなりを提出し扶養に入る→約3か月後に受給開始(自己都合退社の場合)→旦那さんの会社に受給することを伝える→扶養を外れ、保険証を返し、社会保険の資格喪失証明書を貰う→国保、国民年金に加入→受給が終わる→扶養に戻るなら、また受給資格者証を提出する→新しい保険証が届いたら役所に行って国保と年金を外れる。
自己都合であれば申請から受給まで4カ月ほどかかります。
その間は扶養に入っていられます。
すぐに受給するのであればハローワークに行き(離職票などもって)手続きをすればその後説明会があり、受給資格者証が貰えます。
原本を提出すると受給するときに面倒なので、コピーではだめなのか、原本なら確認後すぐ返却してもらえるのか確認してください。
そして、受給するときは扶養を外れるように旦那さんの会社に報告し、外れます。もし受給後も扶養に入るようならまた受給資格者証を提出します(受給完了したというのが記載されますので、それが証明になります。)
整理すると...
旦那さんの会社に確認→離職票が届く→職安にいき手続き→一週間後くらいに説明会があり、そこで受給資格者証を貰える→原本なりコピーなりを提出し扶養に入る→約3か月後に受給開始(自己都合退社の場合)→旦那さんの会社に受給することを伝える→扶養を外れ、保険証を返し、社会保険の資格喪失証明書を貰う→国保、国民年金に加入→受給が終わる→扶養に戻るなら、また受給資格者証を提出する→新しい保険証が届いたら役所に行って国保と年金を外れる。
交通事故被害者で業務委託契約(一人親方)を解除されてしまったものです。
加害者に再就職までの休業損害を請求したいのですが・・・
事故以前は日給制の業務委託で建設業の親方として働いていました。
事故は追突事故で過失は10:0で加害者10です。
加害者は任意保険未加入で自賠責保険しかない人です。
事故後3カ月で仕事を契約解除されました。それまでの休業損害は支払っていただいています。
治療は6カ月かかり後遺障害診断書を保険会社に提出してあり結果を待っているところです。
3カ月分の治療費と休業損害費用等で110万円かかっています。
医師の指示もありほぼ毎日のリハビリ治療をしていました。
以上のような状況の場合に治療期間内の休業損害(3か月分)は請求できるのでしょうか?
また、再就職に向けて求職活動を約1カ月していますが、この期間の休業損害は請求できるのでしょうか?
後遺障害の結果後に示談交渉になると思うのですが、それまでの期間の生活がとても不安です。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願い致します。
加害者に再就職までの休業損害を請求したいのですが・・・
事故以前は日給制の業務委託で建設業の親方として働いていました。
事故は追突事故で過失は10:0で加害者10です。
加害者は任意保険未加入で自賠責保険しかない人です。
事故後3カ月で仕事を契約解除されました。それまでの休業損害は支払っていただいています。
治療は6カ月かかり後遺障害診断書を保険会社に提出してあり結果を待っているところです。
3カ月分の治療費と休業損害費用等で110万円かかっています。
医師の指示もありほぼ毎日のリハビリ治療をしていました。
以上のような状況の場合に治療期間内の休業損害(3か月分)は請求できるのでしょうか?
また、再就職に向けて求職活動を約1カ月していますが、この期間の休業損害は請求できるのでしょうか?
後遺障害の結果後に示談交渉になると思うのですが、それまでの期間の生活がとても不安です。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願い致します。
休業損害は請求できますが、再就職までということにはならないです。後遺障害の重度により、変わりますが、廃業申請し、契約した業務委託で得られていたはずの報酬を損害賠償請求する、ハローワークに申請して失業保険を受理するといった方法が現実的かと。
パートなどの面接で「何か質問はありますか?」と聞かれると少し返答に困ります。
面接で質問した方が良いこと、質問しない方が良いこと(伺わない方が無難なこと)を
教えて下さい。
(自分では気付かずに失礼な発言をしてしまっているかもしれないので、参考までに)
面接で質問した方が良いこと、質問しない方が良いこと(伺わない方が無難なこと)を
教えて下さい。
(自分では気付かずに失礼な発言をしてしまっているかもしれないので、参考までに)
先日、ちょうど面接へ行ってきました「何か質問はありますか?」と言われてきました
面接では相手の方も勤務日や時間帯、今までの経験等色々聞いてくださいました。
なので、特に質問もあまりなく。私も結構困ることでもあります。
(事前にホームページやハローワークの求人等で情報収集していたということもありますが)
質問した方が良いこととしては
仕事の内容は、働いてみないと具体的なことがわからないと思ったので
自分がもし働くことになったら具体的にどんな業務に就くことになるのか聞きました
(私の場合は看護師で外来か病棟か、その中での具体的な業務等)
それから、未経験な分野だったので指導等がどのように行われるか聞きました
質問しない方が良いことは
働く気が本当にあるのか、わがままともとられそうな質問は避けたほうが良いと思います。
あまりにも自分の都合を主張しすぎる事
例えば:残業はどのくらい、休日はとれるかを繰り返し続けるようなこと
事業者にとって不快に思うことは避けることでしょうね☆
でも、面接をする上での立場でも少しかわるかもしれません。
本当に倍率が高い職種で、頑張って就職したい場合。
→とにかくそこで働きたいという意思、興味があるということを伝えて質問をすること。
(質問がその仕事に対する意欲・自己アピールにもなるということ)
一応面接を受けてみて条件を確認して、決めようか。程度で、事業者側が人手不足で必要としている場合。
他にも就職するあてがある場合など。
→自分の都合をどの程度聞いてくれるか、仕事の内容についての具体的な要望について等質問をする。
面接では相手の方も勤務日や時間帯、今までの経験等色々聞いてくださいました。
なので、特に質問もあまりなく。私も結構困ることでもあります。
(事前にホームページやハローワークの求人等で情報収集していたということもありますが)
質問した方が良いこととしては
仕事の内容は、働いてみないと具体的なことがわからないと思ったので
自分がもし働くことになったら具体的にどんな業務に就くことになるのか聞きました
(私の場合は看護師で外来か病棟か、その中での具体的な業務等)
それから、未経験な分野だったので指導等がどのように行われるか聞きました
質問しない方が良いことは
働く気が本当にあるのか、わがままともとられそうな質問は避けたほうが良いと思います。
あまりにも自分の都合を主張しすぎる事
例えば:残業はどのくらい、休日はとれるかを繰り返し続けるようなこと
事業者にとって不快に思うことは避けることでしょうね☆
でも、面接をする上での立場でも少しかわるかもしれません。
本当に倍率が高い職種で、頑張って就職したい場合。
→とにかくそこで働きたいという意思、興味があるということを伝えて質問をすること。
(質問がその仕事に対する意欲・自己アピールにもなるということ)
一応面接を受けてみて条件を確認して、決めようか。程度で、事業者側が人手不足で必要としている場合。
他にも就職するあてがある場合など。
→自分の都合をどの程度聞いてくれるか、仕事の内容についての具体的な要望について等質問をする。
関連する情報